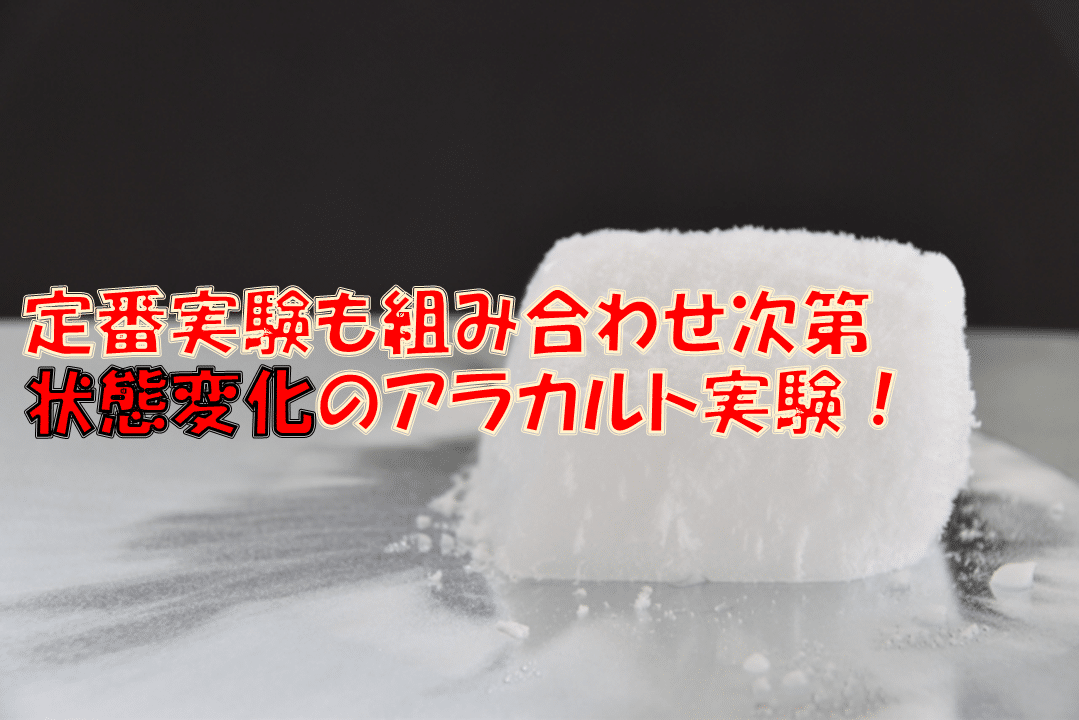状態変化といえば、小学校から水の三態を取り扱います。
中学校では水以外について取り扱ったり、赤ワインの蒸留を行ったりしますね。
まずは三態について知り、粒子性について深めながら学習を進めていく。
ただし、ここまでは基本的に全て大気圧(1気圧)下での話になっています。
もちろん、先生によっては富士山の頂上での水の沸点(87℃程度)の話とか、エベレストの頂上での水の沸点(70℃程度)の話をされる方もいらっしゃると思いますが、圧力との関連性は少し触れる程度かと思います。

知っている生徒も少なくない印象です
高校課程に入って、状態変化に本格的に圧力の概念が入ってきます。
今回はこの圧力を意識した実験も紹介します。
ただし、1つ1つの実験はそこまで時間がかかるものではありませんし、取り扱いの都合上、生徒実験ではなく演示実験の形態のほうが学校の実態に合うものもあると思います。
そこは個々の学校の事情に合わせてアレンジ下さい。
エタノールとドライアイスで-72℃の液体を作る
器具・試薬と実験の概要
使うのはもちろんエタノールとドライアイス、および軍手とビーカーくらいでしょうか。
ドライアイスを使うので注意も必要です。
具体的には超低温のため、直接触れてはいけない(必ず手袋をする)とか。
また、二酸化炭素による酸欠も考えられるので、換気に注意しなければいけないとか。
やることはビーカーにエタノールを注ぎ、ドライアイスを入れるだけ。
エタノール水溶液の凝固点が70wt%で-50℃程度、80wt%で-67℃程度、90wt%で-113℃程度となっています。
また、二酸化炭素(ドライアイス)の昇華点は常温で-79℃だからこそできる実験でもあります。
バラやカーネーションなどを入れて瞬間的に凍らせてみたり、バナナや人参などを凍らせてクギを打ち込んでみたりするようなものは有名ですね。
似たような実験でよくあるものとしては液体窒素を使うものがあるかと思います。
ただ、エタノールとドライアイスの組み合わせで行うメリットや意義がいくつかあると私は感じています。
エタノールとドライアイスによるメリット(管理面と価格面)
同じような実験を液体窒素で行おうとすると、保存用のデュワー瓶も必要になってきます。
すでにある学校ならいいかもしれませんが、新たに購入を検討するとちょっと二の足を踏んでしまうような価格だと思います。
業者によっては数日単位でのレンタルも行っているところもあるようです。
この点、ドライアイスであれば、紙でくるんでスチロール箱の中に入れて(冷凍庫で)保存することで一晩くらいなら相当量を保管することができます。
エタノールとドライアイスによるメリット(指導面)
これについては感覚的なものになるかもしれませんが、授業を受ける生徒の目線で考えると、冷却する(温度を下げる方向)で行う実験のほうがよいと感じています。
マイナス70℃の世界を体感してもらうのに、すでに出来上がった液体窒素を使用するのは味気ない。
どうせなら、常温からエタノールの温度を下げて-70℃の世界を作る過程も見たほうが意義があるのではないかという考えです。
また、小学校や中学校で行ってきた実験は、どちらかというと加熱する(温度を上げる方向)の実験が多いと思っています。
安全面やその他もろもろの理由でできないのだと思うのですが、だからこそ高校生相手にはこの方法がいいのではないかと感じました。
ここまでのまとめ
エタノールにドライアイスを加えることによって-72℃程度の液体を作るのは、すでに多数、動画投稿もされています。
小学生の自由研究レベルかもしれません。
ただ、やはり実物に触れるというのは意義があります。
また、この実験であれば、中学校でも見せ物として取り扱うこともできるのではないでしょうか。
水の減圧沸騰(100℃以下での水の沸騰)
器具・試薬
水・沸騰石・丸底フラスコ・ゴム栓・マッチ・ガスバーナー・スタンド
実験の手順と概要
①丸底フラスコに1/3程度水を入れ、沸騰石を加えてガスバーナーで加熱します。
②しばらく沸騰させて空気を追い出します。
③水が残っていることを確認して加熱をやめ、ゴム栓をします。
④やけどに注意して冷水で冷やします。

掲載されている教科書もあると思います
水蒸気が冷却され凝縮し、それにともないフラスコ内の圧力が下がるため、100℃より低い温度でも水が沸騰する様子を観察することができます。
注意点
単純な実験ですが、生徒にとっては感動も小さくないようです。
だからこそなんですが、割と飽きずに観察を続けたりもします。
そうすると、どうなるかというと‥
どんどん減圧が進んでしまい‥
ゴム栓が丸底フラスコの中に吸い込まれてしまい、取り出せなくなってしまいます(笑)
ゴム栓は、丸底フラスコの口径に対してピッタリのものではなく、もう1号大きいサイズのものを使うことを強く推奨します。
二酸化炭素の液体の観察
器具・試薬
圧縮発火器・ドライアイス・軍手
実験の概要
圧縮発火器の少量のドライアイスを入れてピストンを勢いよく押し込むだけです。
また、ピストンを引いて圧力を下げるとドライアイスに戻る様子も観察することができます。
※液体になったことを観察したらすぐにピストンを引いて減圧する
昇華する物質の例としてよく出てくるのが二酸化炭素(ドライアイス)。
その液体の状態を観察することができる実験です。
繰り返しになりますが、取り扱いの観点では注意も必要です。
具体的には超低温のため、直接触れてはいけない(必ず手袋をする)とか。
また、二酸化炭素による酸欠も考えられるので、換気に注意しなければいけないとか。
あとは、密閉してしまうと、圧力が高まって破裂する危険性もありますね。
下記の動画は東京消防庁による動画です。
まずは危険性を把握しましょう。
その上で、もし二酸化炭素(ドライアイス)の液体を見せる場合には、やはり圧縮発火器を使うのがオススメです。
米村でんじろう先生の実験動画もありますが、量が多すぎて怖くてできません‥
あとは、簡易的にビニールチューブで行っている学校さんもあるようですが、ビニールチューブがどれくらいの圧力まで耐えることができるかがわからないのでこればかりはなんともいえません。
この方法でやる場合には必ず事前に予備実験を念入りに行って下さい!
事故が起こっても当方は一切責任を負いません。
まとめ
状態変化については、圧力の概念を合わせて考えるからこそ実験の幅も広がります。
実験をしながら状態図を追いかけてみてもいいと思いますし、蒸気圧曲線だけを取り出してにらめっこするのもいいと思います。
その一方で、教員側が安全面に配慮しなければいけないことも増えてきます。
事故を起こさないように注意しながら、より実感の伴った理解につながるといいですね!