部活動の負担は近年メディアでも取り上げられています。
その是非についてはここでは議論しませんが、実態をまとめておきます。なぜ部活の顧問が負担と言われるのか、どういう現状があるのかまとめました。
その上で自分自身がどのように関わっていくのか、身の振り方を考えて行く必要があります。
そもそもが負担
運動部顧問には常に生徒のケガのリスク

生徒の管理をすることは教員の仕事ですが、その時間が増えるだけで十分負担増です。
おまけに、運動部であれば生徒のケガにも気をつけなければいけません。やってみると、体育の先生がケガに気をつけて授業する大変さがよく分かります。
私立学校では、保健室に連れて行って終わりということでも、公立校では「念の為に病院に連れていく」ということもしばしばあります。

自分が働いていた公立校では「首から上にモノがあたったら病院につれていく」という雰囲気でした。
また、生徒の生命の危機に直結する部活動もあります。下に例を挙げると
水泳部やボート部は水の事故と隣り合わせです。一歩間違うと生徒が水死しかねません。教員の中でも定期的に救急救命の講習を受けている方もいました。
登山部も遭難の危険性と隣合わせです。山の天気は変わりやすいですし、事前に天気も調べて置かなければなりません。万が一のルートも事前に練っておかねばなりません。天候が悪化した場合や生徒がケガした場合に、どのタイミングで休憩を取るのか、ルートを変更するのかなど的確な判断も求められます。
2017年に起こった冬山での登山部員が巻き込まれてしまった事故は記憶に新しいと思います。

私も元・登山部でしたが、ハイキングやキャンプが主体のアウトドア部に近い感じでした。自分が足を引っ張りかねないので登山部の顧問は拒否させてもらっています。
薬品を扱う科学部・化学部・理科部もそうです。ただの火傷なのか、薬品によるものなのか、特別な対応は必要ないのかなど判断が求められます。高い薬品を使いたい場合などに部費の徴収のしかたが問題になることもあります。
野球部やゴルフ部は使う道具が危険です。また、打球が直撃した場合などは目も当てられません。野球は接触プレーも多いので、そういうケアも必要です。
複数の生徒集団を管理する負担
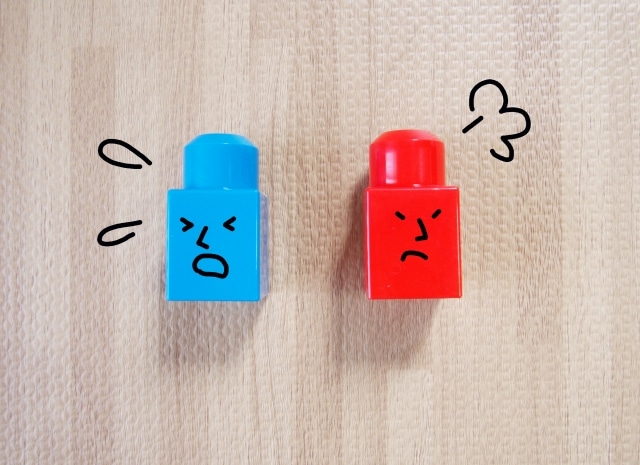
クラスという生徒集団の管理だけでも大変なのに、部活動という別の生徒集団も管理することになると、負担は一気に倍増します。
名簿作りに始まり、集金から会計処理、保護者会の運営など、学年でやっている作業を部活に対してもやらなければいけません。学年の仕事であれば割り振りをしたり、複数の教員で確認しながらできることも、部活に対しては少ない人数で回さなければならないのです。単学級の先生が大変なのと同じ理屈ですね。

集団になると人間関係のトラブルも増えますね
部活動はクラスの集団とは異なり、異学年が交流する機会であり、生徒にとっても学ぶことも多いです。
しかし、学年間で部活に対するモチベーションが違う、男女間でモチベーションが違う、レギュラーに選ばれた選ばれなかったなど、ケアしなければいけないことが多いのです。
チームスポーツか個人競技かでも変わってきます。サッカー、バスケ、バレーボール、野球などはチームワークも必要になってきます。ミスを連発した生徒や部のルールを破った生徒への指導を全体の前でするのか、個別にするのか。またどのタイミングでフォローするのかも考えなければいけません。
学業と部活動のバランスのケアという負担
学業と部活のバランスも問題です。
勉強しない、宿題も出さないのに部活動には参加する生徒もいます。しかし、優先順位は基本的に「勉強>部活動」です。義務教育である中学校ならなおさらです。高校ならば留年という可能性も出てきます。
全国大会に出場するような学校や、全日本レベルの生徒、プロを目指している生徒ではこの優先順位が崩れている場合もあるかもしれません。しかし、勉強をしていないのに部活にだけ参加している生徒は、周囲に悪影響を及ぼすことも少なくありません。
あいつ宿題を出してないくせに部活だけはくるんだぜ
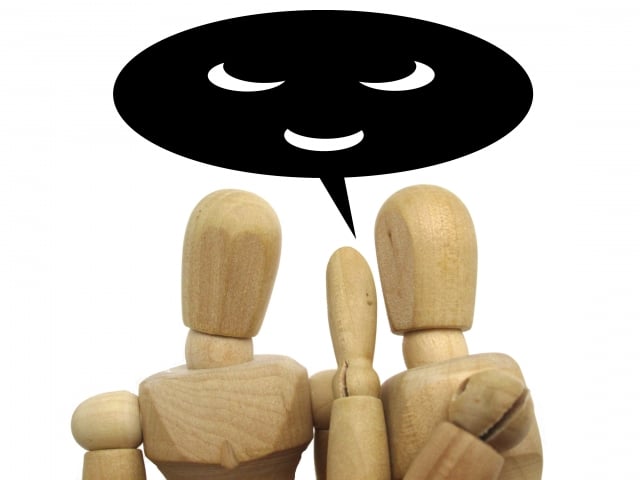
子どもたちはお互いのことをよく見ています。そして、不公平な指導には反発します。このバランスをどのようにとるのかのさじ加減も重要です。

こちらが不公平な指導をしていると、本当に伝えたいことが伝わらなくなります!部活指導の不公平がきっかけになって学校生活のトラブルが拡大したケースも見てきました・・・
学校全体で、「勉強をきちんとできていない人は部活動に参加できない」という方針を明確にしているところはある意味でやりやすいです。逆に、そのあたりを曖昧にし、顧問の裁量に任せている場合は指導が統一されず不公平感がでてしまいます。
野球部は宿題していなくても部活に出られるんだぜ
もちろん、学校のグラウンドではなく外部の施設を利用する部活もあります。その場合、宿題を終わっていない生徒を学校に残すのか、練習場所に引率して宿題をさせるのかも判断しなければなりません。
中学以上だと教科担任制なので、宿題をきちんと出しているのかを把握することも困難です。タダでさえお互いに忙しい中、たくさんの担任の先生とコミュニケーションを取ることも求められますし、対応の落とし所を探すのも大変です。
教科担当が担任の先生に宿題の未提出状況を伝え、担任の先生が部活の練習中に来る場合もあります。その生徒を、教室で残して宿題を終わらせてから練習に戻すのか、必ず家でやって翌朝の始業前に提出する約束で練習に参加させるのかなど、担任の先生との連携も必要です。
逆に登校拒否や長期欠席しがちな生徒が部活動を1つのモチベーションとしている場合もあります。課題の未提出をどこまで許すのか、担任がチェックするのか、顧問がどのタイミングで声掛けをするのか。きちんと連携していないと、顧問の不用意な一言で、長期欠席に逆戻りしてしまう場合もありえます。

最終目標は学校復帰です。顧問、担任、保護者で落とし所を探りつつ連携をとらないとトラブルにも発展しかねません!
掛け持ちの負担
部活動を掛け持つことは、もはや当たり前の学校がほとんどです。
生徒数の割に部活の数が多い、部活の数の割には教員の数が少ないという問題は全国のほとんどの学校で抱えていると思います。また、私立学校の中には、部活動をウリにしている学校もあります。そのような学校では3つ以上の部活を掛け持つ場合も考えられます。
上の項目でも述べましたが、部活動も1つの集団です。1クラス30~40人程度の集団とはまた違いますが、異学年が混ざった生徒集団です。クラス経営であれば、自分が主として生徒の前に立ちますが、部活動ではたいてい複数の先生が顧問になります。
主顧問であれば、方針の決定も生徒とのやりとりも、クラス経営と同じように自分の意思を反映させやすいです。しかし副顧問である場合には、主顧問の先生の意見を尊重しながらバランスをとらなければいけない場面も多いです。この点でやりにくさを感じることも少なくありません。

私は自分の予定を他の先生に決められてしまうのがイヤなので、一緒に組む先生を見てから場合によっては主顧問を引き受けてしまいます。
では、全ての部活動で主顧問になればやりやすいかと言われればそうでもありません。担任をもって、主顧問も複数もつと、生徒集団を3つも4つも管理しなければいけません。それぞれ部費の管理をしたり、部内の様々な調整やご家庭への連絡など、やらなければいけないことは少なくありません。

実際のところ、お金の管理だけは副顧問の先生にお願いする、大会の引率だけは協力していただくなどうまくコミュニケーションをとって分担できている先生がたもいらっしゃいます。しかし、体調不良の先生やご家庭の事情(育児や介護など)でなかなか協力していただくのが難しい先生と組む場合もあります。
私の場合は、運動部については幸い専門の競技なので主顧問として技術指導やチーム作りをしています。副顧問の先生ともうまく連携をとり、私が通院するときは練習を見てもらうなどしています。また、大会の引率とお金の管理もやってもらっています。
専門性という負担
自分の専門の場合でも負担
芸術科目の先生に多いですが、当該教科と関連性が高い部活を任せられる場合も多いです。美術の先生なら美術部、音楽の先生なら吹奏楽部や合唱部などです。ひどい時には音楽の先生が吹奏楽部も合唱部も担当している場合もあります。
特に音楽関係は毎日練習しないと上達しません。そのため、顧問が指導する日、自主練の日、パートごとに合わせる日、全体で合わせる日など調整しなければいけません。また、楽器を自分でもっている場合はいいのですが、金銭的負担も大きいこともネックです。買うのか、学校のものを貸すのか。
運動部の顧問で、幸いにも自分の専門の部活になった場合でもトラブルが待っていることもあります。いわゆる「前の顧問の先生のほうがよかった」という場合です。
◆今までよりも練習の量が増えた
◆今までよりも練習の量が減った
◆前の先生と重要視することが違う
◆新しい先生も専門だけど前の先生のほうが上手かった
◆etc…
異動したら自分のチームにする(自分のやり方でできるようになる)のに3年かかるという先生もいます。前の顧問の先生の影響が残っているとやりにくいのも事実ですが、生徒との信頼関係の構築が早ければ、比較的短時間で自分のやり方が浸透します。
専門外の競技の場合の負担
自分の専門外の部活の顧問を担当することになった場合、悲惨な状況になることも少なくありません。
ルールがわからない、適切な練習がわからない、新入生をどう指導したらいいかわからない(異動直後は本当に切実)など悩みはつきません。また、的はずれな発言をして生徒からの信頼を失ってしまうのも早いです。
結局はその先生の人柄によるのですが、生徒を頼りにしながら順応していくしかありません。今までどういう練習をしてきたのか、どういう戦術なのか、教えてもらいながら練習を組み立てていくしかありません。

私も一度だけ専門外の運動部の顧問をさせられましたが、生徒と協力しながら作っていく感じがいいのかなと思います!
そんな先生たちをサポートする教材DVDもあります。4月頃に「全国ベスト○の△△高校の練習メニュー」「□□部を最初から丁寧に技術指導していく方法」など案内が届くことが多いです。ただし、DVD3枚組で¥7,980とか¥9,980というものがほどんどです。
学校が負担してくれるわけもなく、私も初任者のとき自腹で29,800円のものを購入した経験があります。ただDVDの内容を全部やれるかというと、施設の問題や練習時間の問題でできないことも多々あります。そもそもDVDをちゃんと見る時間も取れません。
また、体育の先生にありがちたと思っているのですが、引き受け手がいない運動部の顧問をお願いされることが多い印象です。管理職側も「体育の先生なら何でもできるでしょ!」と割とオールマイティーな人と見ていると思います。
自分が知っている体育の先生の例でいうと、「バレーボールが専門なのに女子ソフトボール部」を任された男性教員、「ソフトボールが専門なのにバドミントン部」を任された女性教員などがいます。挙げればキリがありません。

未経験のバスケットボール部の顧問をやらされた時は本当に毎日が苦痛でしかたありませんでした。
審判の負担

これは本当に大変です。
バスケットボールやサッカーの審判は、生徒(選手)以上に走り回ることになります。生徒の部費が審判のドリンク代で消えるという学校もありました。
自分が専門の競技の場合や、観戦する趣味がある競技の場合はルールは問題ないと思います。しかし、専門外の場合はルールを覚えることに始まり、審判の手の形、笛を吹くタイミングと回数など、覚えることが多いです。
そして、審判の講習会や検定もあります。練習試合でも公式戦でも、お互いの学校から審判を出し合ったり、他校の審判を担当することがあります。大人が練習してできるようにならなければいけないというのはかなりの負担です。
若いうちはまだ身体も適応できますが、年齢が上がると身体の動きも鈍くなり、ケガのリスクも上がります。そのため、まだ慣れていない若手に審判の役割がまわってきます。初任者だと授業とクラス経営だけでも大変なのに。。
まとめ
以上のように、部活の顧問はとにかく大変です。
ただでさえ多忙な教員に教育課程外からトドメを刺しにきているといっても過言ではありません。
顧問が足りず、半ば強制的に顧問をもたされるのが現状です。
手当などの待遇だけでもせめて改善されれば、とも思う方は以下の記事もご参照ください。
.jpg)


-150x150.jpg)
コメント